
本記事では、企業における生成AI活用をより一層推進するため、生成AI環境をリニューアルした取り組みをご紹介します。多様なモデルを使えることで、業務でのAI活用が広がることを目指しています。
背景
当社では、Azure OpenAI Serviceをベースに生成AI環境を社内展開していました。構築した2023年当時は、OpenAI社のモデルを使えることが最優先課題であったため、他のモデルのサポートは見送られました。API基盤としては、Azure API Managementで構築して、利用者にAPIキーを提供していました。さらに、独自開発したアプリケーション1により、Web UIでの利用方法も提供していました。
しかし、2025年現在、様々なモデルが台頭しています。特にAI駆動開発のために、Anthropic ClaudeやGoogle Geminiなどの利用を望む声が社内で高まりました。AIチャットアプリケーションについても、Web検索等の機能追加が進まず課題を抱えていました。
また、Amazon BedrockやGoogle Vertex AIで扱えるモデルが充実してきたこともあり、Azure OpenAI Serviceありきの仕組みを見直す好機でもありました。こうした背景を踏まえて、社内の生成AI環境をリニューアルしました。
AIゲートウェイ
AIゲートウェイは、クライアントと生成AIサービスの間で、組織内の生成AIトラフィックを制御します。セキュリティ、モニタリング、ロギング、コストトラッキングなどを一元管理できる点が特長です。当社の従来環境では、Azure API Managementが相当します。
リニューアルの検討においては、Amazon BedrockとGoogle Vertex AIも利用することを念頭に、以下の点を重視しました。
- 様々なLLMが使える:ClaudeにもGeminiにもその他のLLMにも対応
- OpenAI互換APIで使える:既存のプログラムやオープンソース実装との親和性のため
- 独自実装は最小限に:メンテナンスの負荷を抑制したい
Amazon BedrockとGoogle Vertex AIには、OpenAI互換APIが提供されていません。既存のAzure API Managementを活かして両サービスを統合するには、Azure OpenAI Serviceの場合と比べて相応の手間がかかりそうでした。
そこで、オープンソースのLiteLLM Proxyを新たに採用することにしました。
LiteLLM Proxy
LiteLLM Proxyは、様々なAIサービスとの接続をサポートするAIゲートウェイ実装です。Amazon Bedrock、Azure OpenAI Service、Google Vertex AIにも対応しています。開発とリリースが活発で、新モデルへの対応も迅速です。
構築にあたって特段難しい部分はなかったのですが、以下の点を工夫しました。
- モデル定義の設定ファイルを3つのAI基盤サービスで分割して、メンテナンスしやすく
- LiteLLM側に単価情報のないモデルは、設定ファイルに単価情報も追記
- APIキー利用者が指定するモデル名は、平易で分かりやすい表記に(クラウドサービスのモデルIDを流用しない)
- ログはAmazon S3に保管して、Amazon Athenaでコストとトークン数を集計可能に
なお、AIゲートウェイと各クラウドの生成AI基盤サービスとの疎通は当社Webプロキシ及びインターネット経由であり、閉域接続ではありません。当社で利用するAIエンドポイントへのアクセスについては、当社のグローバルIPアドレスからのみ許可する接続元IPアドレス制限をかけています。
LiteLLM Proxyベースの新たなAIゲートウェイは、以下のモデルに対応しています。
- Chat Completion: Amazon、Anthropic、Cohere、Google、Meta、Mistral AI、OpenAI各社の主要LLM
- Embeddings: Amazon、Cohere、Google、OpenAI各社の埋め込みモデル
- その他: リランク(Amazon、Cohere)、画像生成(Amazon、Google、Stability AI)、オーディオ(Google、OpenAI)
Chat Completionだけでも約40のモデルに対応し、選択肢が大幅に増えました。AIゲートウェイの利用者は、払い出されたAPIキーで上記のモデルをすべて使えます。
AI駆動開発での活用
AI駆動開発は、当社のAIゲートウェイ利用者にとっても主要なユースケースです。LiteLLM ProxyがOpenAIとAnthropicの互換APIに対応するため、AIゲートウェイ経由でCline、Roo Code、Claude Code等のAIコーディングツールを使えるようになりました。
Clineの場合、開発計画を考えるPlanモードとコードを生成するActモードで異なるモデルを指定できます。例えば、Planモードで推論性能の高いo3、Actモードでコーディング性能の高いClaude Sonnet 4といった使い分けも可能です。
LLMの性能向上に伴い、AI駆動開発もさらに加速すると思われます。AIゲートウェイが新しいモデルをサポートすれば、ツール側でも設定を変更するだけで最新モデルを活かせるので、開発者体験の向上につながると考えています。
AIチャットアプリケーション
AIチャットアプリケーションについては、独自開発では社員の期待する機能充実ペースを確保できなかった反省を踏まえて、開発が活発なオープンソースアプリケーションを検討しました。その結果、Open WebUIを採用しました。他の候補と比較すると、構築時の設定ファイルと環境変数の記述量が少なく、細かい設定は管理画面で可能なため、本運用に向けた調整が容易でした。
Open WebUI
Open WebUIは多機能なAIチャットアプリケーションで、複数モデルの同時実行、Web検索、ナレッジベース、プロンプト管理、コードインタープリター、アーティファクトなどの機能を備えています。前述のAIゲートウェイ(LiteLLM Proxy)と接続することで、様々なモデルを利用できます。

拡張性についても考慮されており、Open WebUI本体のソースコードに手を加えずに、機能を追加できるFunctionsという仕組みが用意されています。検討と動作確認のうえ、以下の2つの機能をFunctionsで実現しました。
アップロードファイルをLLMに全文渡すオプション
ドキュメントをベクトル検索するか全文をLLMに渡すかは、グローバル設定としてどちらか一方にする必要があります(2025年7月現在)。ナレッジベースの登録が充実していくと、LLMのコンテキストウィンドウの観点からベクトル検索が不可欠です。しかし、チャット画面で少数のファイルをアップロードする場合は、全文をLLMに渡して質問するほうが望ましいケースも十分にあるため、ユーザーが必要に応じて選択できるようにしました。
ユーザーIDをAIゲートウェイのログに含める
AIゲートウェイのログにはAPIキーの利用者を示すフィールドがあります。AIチャットアプリケーションからAIゲートウェイ経由でLLMを利用すると、誰が使ってもアプリケーション用に払い出されたAPIキーのエイリアスが記録されます。このままだとアプリ利用者ごとの集計が難しいため、別のフィールドに記録されるように調整しました。
他のシステムとの接続
Open WebUIは、OpenAI互換APIを持つAIエージェントとの接続が可能です。モデルの代わりにAIエージェントを選択して、利用できます。独自に構築した社内文書検索エージェントや、リサーチエージェントをAIチャットアプリケーション上で使えるようにしています。
また、Open WebUIは、MCPサーバーとの接続もサポートしています。ただし、Open WebUI独自のリバースプロキシ実装を経由する必要があり、本格的な活用には至っておりません。MCPサーバーとの連携は、AIの扱えるデータと回答の幅が大きく広がる可能性を秘めているだけに、今後の課題となります。
リニューアルを振り返って
当社の生成AI環境の構成をリニューアル前後で比べると、以下のとおりです。
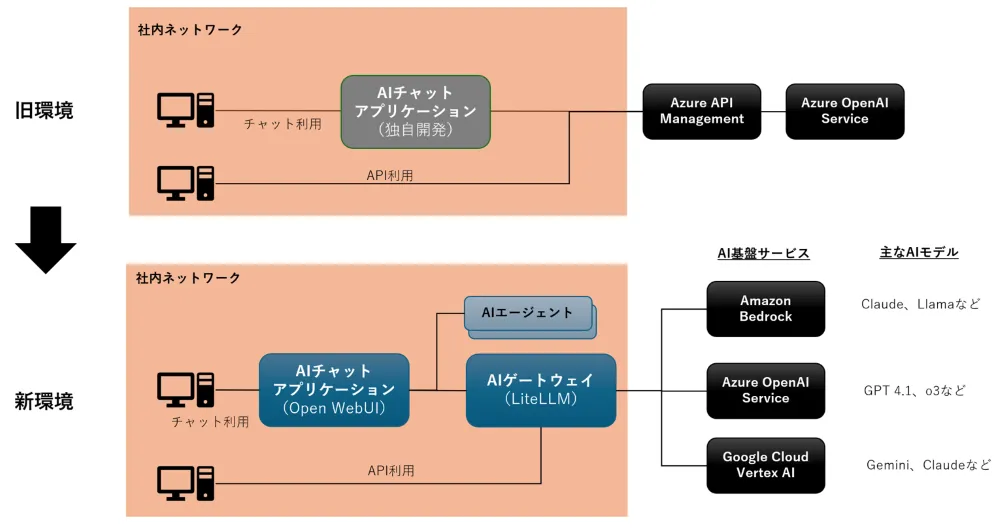
多様なモデルをサポートするために複数のAI基盤サービスに対応する必要があり、そのためにAIゲートウェイを中心とする構成に変わりました。
リニューアルの結果、AIゲートウェイとAIチャットアプリケーションのいずれも、アクティブユーザーとAPIリクエストが大幅に増加しました。モデルの選択肢が生成AIを活用するモチベーションに、AIチャットアプリケーションの各種機能がユーザー体験の向上につながったと考えています。
今回のリニューアルでは、オープンソースソフトウェアの組み合わせで、多様なLLMのサポートと拡張性を両立できたと感じています。今後も、会社全体でAIスキルを向上させていく基盤として、生成AI環境の強化を推進していきます。
Footnotes
-
正確には、オープンソースのChatGPTクローンアプリケーションをforkして追加開発したものですが、本家の開発は既に停止しています。 ↩

